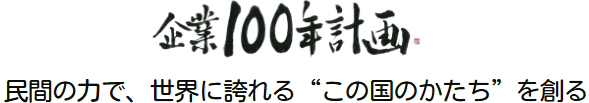1.“思想”“信条”“優越感”とは
◆【思想】とは、「人として、こうあるべき」というような大きなものの見方、考え方のことです。人が、自分自身や自分自身の周囲について、あるいは自分自身が感じて思考できるモノと事について抱く、あるまとまった考えのことです。
◆【信条】とは、堅く信じている事柄のことです。キリスト教会で、その信仰を明白に表現することでもあります。
◆【優越感】とは、自分自身(自民族)が他者(他民族)よりも優れていると感じることです。ここから生じる自己肯定(自らの存在意義を正当化する)の感情でもあります。
2.紀元前からある西欧人の“一神教”と“唯一神教”
(1) “一神教”とは
◆【一神教】とは、「神」は唯一(ただ一つ)であり、普遍的に神と呼ばれる至高の存在であるという信仰です。
◆通常は、「ユダヤ教」「キリスト教」「イスラム教」の3つが、その典型とされています。複数の神々を崇拝する我が国の「多神教」と異なり、一つの神のみを信ずる信仰を説く宗教のことです。
◆「一神のみを崇拝する」といっても、その崇拝の仕方や神観念の相違によって、「一神教」はさらに「唯一神教」「拝一神教」「単一神教」「交替神教」などに分類されますが、「狭義の一神教」とは、「唯一神教」のことを指します。
(2) “唯一神教”とは
◆【唯一神教】においては、「崇拝される神」が万物を支配する「唯一の神」であり、他の神々はそのままでは容認されません。宗教史的にみれば、他の神々は神ではなく、諸霊として格下げされたり、その実体を失って「唯一神」の属性的存在となる場合が多いです。
◆このような【唯一神教】には、他の教えを邪教とする排他的な面と、すべての人々に「唯一神」の恩恵が及ぶという包容ある側面とがあります。
◆ゆえに、【唯一神教】は世界に向かって「崇拝する神の教え」を広めようとする宣教の傾向を持つのです。
① 民族からの視点
◆【唯一神教】の救済の対象を、「一つの民族」とした場合、「他の民族」は神の救済の対象外とされやすいです。
◆この教えが、終末思想(人類の最後)と結びついた場合、「他民族排斥」や「民族闘争」になりやすいのです。
② 宗教からの視点
◆【唯一神教】の救済の対象を、「一つの宗教」とした場合、「他の宗教信者」は神の救済の対象外とされやすいです。
◆この教えが、終末思想と結びついた場合、「異端排斥」や「異端弾圧」「宗教戦争」になりやすいのです。
③ 地球全体(世界)からの視点
◆【唯一神教】の救済の対象を、「地球全体の民族・宗教」とした場合、人類全体が崇拝する神の教えたる【唯一神教】による救済の対象と見なされることにつながります。
◆【唯一神教】を中心にした(論理による)人類愛や、世界平和を希求することになります。
3.“唯一神教”による英国の「白人の責務」
◆白人は、「文明化していない他の人種を、文明化する責務を果たすべきだ」という、白人の世界進出や支配を理想化する観念です。
◆1899年に、米国がスペインとの戦争に勝利してフィリピンなどを獲得した際、英国初のノーベル文学賞作家ジョセフ・ラドヤード・キップリング(1865年~1936年)が、セオドア・ルーズベルト米大統領に贈った詩「The White Man’s Burden」の一節に、「白人の責務を担え,最善の人々を送り出せ」と書いたのが、この言葉の起源です。
4.“唯一神教”によるフランスの「文明化の使命」
◆「文明化の使命」は、単なる植民地政策の偽善や、植民地主義イデオロギーではありません。
◆第三共和政下のフランスは、政府が植民地において「何ができ、何ができないのか」という限界を設定した特定の意味を持ったものとして「文明化の使命(植民地化を正当化する大義名分)」を発明し、それによって「植民地支配」と「民主主義」との矛盾を曖昧にすることができたのです。
5.“唯一神教”による米国の「マニュフェスト・デスティニー(明白な天命)」
◆「マニフェスト・デスティニー」とは、元々は米国の西部開拓を正当化する標語でした。「明白なる使命」「明白なる運命」「明白な天命」「明白なる大命」などとも訳出されます。
◆文明は、古代ギリシア・ローマから英国へ移動し、そして大西洋を渡ってアメリカ大陸へと移り、さらに西に向かい、アジア大陸へと地球を一周する」という、いわゆる「文明の西漸説」に基づいた米国的文明観です。
◆1845年、ジョン・オサリヴァンが用いたのが初出です。この際は、米国のテキサス共和国の併合を支持する表現として用いられ、のちに米国の膨張を「文明化」「天命」とみなして、インディアン虐殺、西部侵略を正当化する標語となっていきました。
6.“人種主義(人種差別)”とは
◆【人種主義】とは、人種間に根本的な優劣の差異があり、「優等人種」が「劣等人種」を支配するのは当然である、という思想・イデオロギー(考え方や信条)です。
「白色人種の優秀性を唱える思想」は、19世紀における【帝国主義】や【植民地政策】の正当化と容易に結びつき、その思想的支柱となりました。
◆一方で、支配された「有色人種」が「白色人種」と対等になれるとは、全く考えられていませんでした。
「非白色人種」への西欧文明の【教化(望ましい方向に進ませる)】の動きは、現地住民との様々な齟齬(そご/双方の食い違い)や、西欧化の遅れによって変質していき、西欧人の文明的な「優越性」を現地住民が完全に理解し、「同化(異なる思想を同じに)」することは不可能であるとする「人種差別的な認識」が普遍的なものとなりました。
◆こうした「白色人種の優秀性を唱える思想」は、西欧に広がり、20世紀初頭にはほとんど自明のこととされていました。
⇒【ヨーロッパ中心主義】参照
◆アフリカにおいては、「文明程度の劣った植民地に、近代文明を伝えることが先進諸国の責務である」といった思想の元に、現地住民への一方的な支配や文化の押しつけ、現地資源の開発などが正当化されました。
この思想は、英国では「白色人種の責務」、フランスでは「文明化の使命」、米国では「マニフェスト・デスティニー(明白な天命)」などと呼ばれています。
7.“ヨーロッパ中心主義”とは
◆【ヨーロッパ中心主義】は、15世紀半ばから17世紀半ばの【大航海時代】に始まります。西欧諸国は大洋に乗り出し、アメリカ大陸や東南アジア島嶼部、北アジアなどの植民地化を進め、文化が世界各地に伝播していきます。ただし、トルコ支配下の東欧・中東・インド・東アジア・東南アジア大陸部においては、在来文明の勢力が強く、当時は西欧文化があまり浸透しませんでした。
◆当時のヨーロッパは、戦乱が相次いでいる有様でしたが、18世紀から19世紀にかけてヨーロッパの経済発展および技術革新の速度は、他の地域のレベルや学問レベルの発展を大きく上回り、技術的・軍事的なヨーロッパの優位が確立しました。中国やインド及びその周辺にも列強国の勢力が浸透し、ヨーロッパ文明は世界を席巻します。この過程で【植民地】になった諸国や、ヨーロッパにならった近代化を目指した地域では、自国の歴史、技術、文化を劣ったものとみなし、ヨーロッパ文明を普遍のものとする価値観が広まりました。
◆【ヨーロッパ中心主義】の内容としては、下記のようなものがあります。
① 哲学の始まりをギリシャからとし、それ以外の地域の哲学は傍系(枝葉の系統)のものとする。
② ヨーロッパ文明を西洋として、それ以外の文明を東洋としてひとまとめにする。
③ ヨーロッパの技術、科学が全時代にわたって他文明のそれに対して優位にあったと見なす。ゆえに、必然的にイスラム黄金時代(8世紀~12世紀)は過小評価されている。
④ ヨーロッパ文明は合理的であるとし、それ以外の文明は非合理的であるとする。